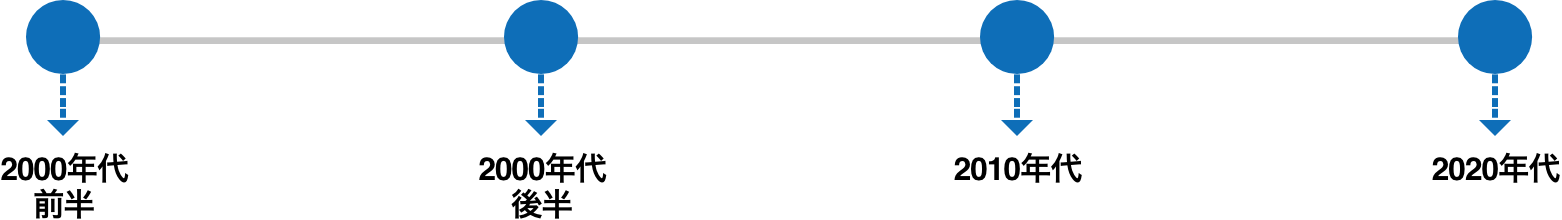時代とともに進化するIP Geolocation技術
2000年の創業から現在に至るまでの25年間、株式会社Geolocation Technologはインターネットの発展と共に歩んできました。
2001年時点で日本のインターネット利用者は約4,700万人でしたが、わずか2年後の2003年には8,400万人を超え、人口の約66%がインターネットにアクセスする環境が整いました。この急速な拡大は、ADSLや光ファイバーなどのブロードバンド回線の普及が加速したことに起因しており、日本国内で「常時接続」が一気に一般化した重要な時期といえます。その後も利用者数は着実に増加し、2023年には1億人を突破。利用率も85%を超えるまでに成長しました。※
この間、IPアドレスを活用したIP Geolocation技術は、広告配信、セキュリティ対策、ジオターゲティングなど、さまざまな用途で重要な役割を果たすようになりました。
2000年当時はまだインターネット接続が固定回線中心で、個人の利用環境も限定的でした。しかし、スマートフォンの普及により、IPアドレスはより動的に、そして多様に変化するようになりました。技術の進化に合わせて、当社のIP Geolocation技術も精度向上と用途の拡大を重ねてきました。
2000年代前半
ブロードバンド元年と
IP Geolocation技術の始まり

2000年代前半は、いわゆる “ブロードバンド元年” とも呼ばれる時代であり、日本のインターネット環境が急速に変化した転換期でした。ADSLやCATVを中心に固定ブロードバンド接続が急拡大し、家庭にも常時接続環境が広がり始めたことで、個人によるインターネット利用が日常化していきます。
1999年に登場したYahoo! BBを皮切りに、2001年にはNTTの「フレッツADSL」が開始され、2002年末にはADSL契約数が500万件を突破。回線速度は1.5Mbpsから8Mbps、12Mbpsへと進化し、家庭でのインターネット体験が劇的に変化しました。
この時代、インターネット利用者数は2001年時点で約6,700万人、人口普及率で約53%に達していました。一方で、企業ではすでに固定IPを活用したインターネット常時接続が標準化し、業務のWeb化・メールインフラの整備が加速しました。
通信技術の変遷
- 2000年:ブロードバンドの本格展開がスタート。
Yahoo! BBの登場により、ADSLが急速に普及。 - 2001年:FTTH(光ファイバー)サービスの商用化開始。
- 2002年:日本のインターネット人口が約8,400万人に到達。
- ISDNからADSLへと主流が移行し、通信速度は数十kbpsから数Mbpsへと一気に向上。
IPアドレス環境の変化
- IPv4が主流であり、企業では固定IPを活用した専用線接続が一般的。
- ISPによる動的IPアドレスの割り当てが家庭向けに標準化。
- プライベートIPアドレスとNAPT(Network Address Port Translation)の導入が進み、IPv4アドレスの枯渇対策が本格化。
- ICANN主導で、IPアドレスの割り当てと管理の国際的なガバナンス体制が強化される。
IP Geolocation技術の軌跡

2000年2月にサイバーエリアリサーチ株式会社を設立した当社は、日本におけるIP Geolocation技術の先駆けとして、IPアドレスから位置情報を判別する独自技術の開発に取り組みました。
当時はダイヤルアップ接続が主流であり、IPの地域性を明らかにするには、全国のプロバイダと契約し、アクセスポイントに実際に接続してIPアドレスを取得・調査するという、地道で手間のかかる工程が必要でした。
この調査思想は、現在の技術にも継承され、当社のIPデータの信頼性を支える根幹となっています。
また、IPアドレスの逆引きやWhois情報、ホスト名やサブドメインに含まれるキーワードの抽出・解析を通じて、地域情報とのマッチングを実現するアルゴリズムも構築しました。
プロバイダごとに異なるキーワードパターンを蓄積し、累計で300万件を超えるマッチパターンを保有しています。
これらはすべて、継続的な調査と検証によってアップデートされており、今もなお拡張・強化を続けています。
私たちは、IPアドレスの見えにくい構造を可視化し、インターネット上の「場所」を明らかにするための技術を、妥協なく追求してきました。
2000年代後半
光回線の普及と
IPv4枯渇への備え

2004年以降、ブロードバンドの主力はADSLから光ファイバー(FTTH)へと移行していきます。
NTTの「Bフレッツ」や「フレッツ光ネクスト」、KDDIの「auひかり」などが全国展開を加速し、2008年には光回線契約数がADSLを逆転しました。
これにより、日本の通信インフラはさらなる高速化・常時接続の安定性を手に入れることとなります。
一方で、IPv4アドレスの枯渇問題がグローバルで注目を集めるようになりました。2007年にはJPNICが「IPv4アドレス在庫枯渇予測レポート」を公開、2008年には世界的な啓発キャンペーン「IPv6 Day」もスタートし、国内でもIPv6導入の検討が進み始めました。
通信技術の変遷
- 2005年:FTTH契約数がADSLを逆転し、日本の固定回線の主流となる。
- 2007年:iPhone(初代)の発表により、スマートフォン時代が幕を開ける。
- 無線LAN(Wi-Fi)の一般家庭への普及が進み、屋内でのモバイル接続環境が充実。
- 無線ブロードバンド(WiMAX)など新たな高速通信方式の登場。
IPアドレス環境の変化
- 2007年:APNICなどRIR(地域インターネットレジストリ)がIPv4アドレス枯渇に関する警鐘を発信。
- IETFやISP各社がIPv6の導入に向けた準備を本格化。
- IPアドレスの分配ポリシーの見直しが進み、組織や用途に応じた割り当てが厳格化。
- キャリアグレードNAT(CGN)のような一時的対応策が注目され始める。
IP Geolocation技術の軌跡

急速に進展したブロードバンド化と、それに伴うインターネット接続形態の多様化は、IP Geolocation技術の精度向上と技術進化を強く後押ししました。
この時代は、全国各地にISPが乱立し、事業統合や淘汰が進む激動の時期でもありましたが、当社はその変化をリアルタイムで追跡し、技術の適応力を磨いてきました。
インターネット通信における経路情報や応答速度を活用した新たな判定技術を確立し、IPアドレスからの位置推定をより現実的かつ高精度なものへと引き上げました。
また、この時期には、国内に存在するIPアドレスのほぼ全域をカバーする体制が構築され、データベースの網羅性が飛躍的に高まりました。
加えて、位置情報判定の信頼性を可視化するための指標として、独自の「CF値(Confidence Factor)」を導入しました。
用途やサービス特性に応じて、ユーザー自身が判定精度を確認・選択できる仕組みを提供し、透明性と実用性の両立を実現しました。
さらに、PHS・3G・WiMAXといったワイヤレス通信の普及により、一部のIPアドレスでは従来の位置情報だけでは十分な判断ができないケースが生じるようになりました。
こうした背景を受け、当社は接続環境の分類や通信経路の特性、組織情報など、位置情報以外の付加価値情報を強化するための調査手法を独自に開発し、情報の網羅性と精度の向上を徹底して進めてきました。
当社はこの時代、変化し続けるネットワーク環境に対応しながらも、精度・信頼性・柔軟性を備えたIP Geolocationデータベースの構築に全力で取り組みました。
IPアドレスという限られた資源を最大限に活かすための挑戦を、私たちは決して止めることなく続けてきました。
2010年代前半
IPv4の限界とIPv6の本格導入

2010年代前半は、インターネットのインフラ転換期ともいえる重要な時代でした。スマートフォンの急速な普及により、個人が常時ネットワークに接続する環境が整い、トラフィックは飛躍的に増加しました。一方、IPv4アドレスの枯渇が現実となり、インターネットの基盤をIPv6へと移行させる動きが本格化します。
通信技術の変遷
- LTE(4G)の全国展開が進み、モバイル通信速度が飛躍的に向上。
- スマートフォン利用率が2010年時点で9.7%、2014年には62.6%に達し、デジタルシフトが加速。
- モバイルWi-Fiルーターの普及により、外出先でも高速通信が可能に。
- IPv6 IPoE方式の商用化により、混雑回避と安定通信のニーズに対応。
IPアドレス環境の変化
- 2011年:APNIC(アジア太平洋地域)がIPv4アドレス在庫の枯渇を正式に宣言。
- 2012年:「World IPv6 Launch」により、Google、Facebook、Yahoo! などの大手がIPv6を正式採用。
- 国内のISPや大学などでもIPv6対応が進展。
- キャリアグレードNATの導入が進み、IPアドレスの共用化が一般化。
IP Geolocation技術の軌跡

2010年代前半は、クラウドサービスが急速に普及し始めた時代でした。
特にAmazon Web Services(AWS)の台頭により、当社でも調査インフラの構築・拡張がかつてないスピードで進み、IP Geolocationに必要な情報の収集・処理体制を大幅に強化することができました。
この時期、当社ではIPアドレスの逆引きを月間で4億件以上実施し、経路情報に関しても400万件以上のIPアドレスに対する調査を毎月行う体制を整えました。
これにより、インターネット上のネットワーク構成の変化をこれまで以上に早く、かつ正確に検知できるようになりました。
さらに、Wi-Fiアクセスポイントの増加やスマートフォンの急速な普及により、ユーザーがインターネット上で自身の位置情報を利用する機会が爆発的に増加しました。
それに伴い、当社が扱うIPデータの量も飛躍的に増大しました。
この膨大なデータに対応するため、従来は調査員の判断に依存していた一部の処理を機械化し、自動化によって対応可能な範囲を大幅に拡張しました。
これにより、毎日のデータ更新を実現し、IP Geolocation情報の鮮度と精度を飛躍的に高めることに成功しました。
当社は、急激に変化するインターネット環境に対し、技術と運用の両面から挑み続けました。
そして、常に「確かな情報」を届けるという責任のもと、より強固で信頼性の高いデータ基盤を築き上げてきました。
2010年代後半
モバイル通信の進化と
インターネット利用の多様化

2010年代後半は、モバイル通信の進化とともに、インターネットの利用環境が大きく変化した時代でした。LTE-Advanced(4G+)やキャリアアグリゲーション技術の導入により、モバイル通信の速度と安定性が格段に向上。
スマートフォン1台で高品質な動画視聴やクラウドサービスの利用が当たり前となり、生活やビジネスにおけるインターネットの存在感がさらに強まりました。
一方、クラウドサービスの普及により、企業の業務インフラも大きく変化しました。オンプレミスからクラウドへの移行が進み、SaaS、PaaS、IaaSの活用が拡大。
あらゆる業種でデータドリブンな意思決定が重視されるようになり、AI・機械学習を用いた分析や最適化が進んだのもこの時期の特徴です。
また、サイバー攻撃や不正アクセスなどのセキュリティリスクも増加し、多層的な防御体制が求められるようになりました。
ゼロトラストセキュリティの考え方が浸透し、ネットワークの構成や接続元に関する情報の重要性も高まっていきました。
通信技術の変遷
- 光回線の高速化、Wi-Fi 6の登場により、家庭内ネットワークの通信品質が向上。
- キャリア各社が5G実証実験を開始(2018年〜)、モバイル通信の次世代化へ。
- IPv6 IPoE対応ルーターの普及により、家庭ユーザーでもIPv6の恩恵を享受。
- フレッツ光ネクストなどの高速通信サービスが都市部を中心に拡大。
IPアドレス環境の変化
- 2019年:RIPE NCC(欧州地域インターネットレジストリ)がIPv4アドレスの完全枯渇を宣言。
- IPv4の市場価格が高騰し、アドレス売買や移転がビジネスとして定着し始める。
- IPv6対応サイトの割合が日本国内でも20%を突破(2019年時点)。
- CGN(キャリアグレードNAT)を介した共有IPの普及により、IP単位での識別が困難になる場面も増加。
IP Geolocation技術の軌跡

2017年、当社は社名をサイバーエリアリサーチ株式会社から株式会社Geolocation Technologyへと変更しました。
この社名変更には、コアテクノロジーであるIP Geolocation技術を一層発展させていくという意志と、単なる調査開発にとどまらず、お客様の課題解決につながるテクノロジーの提供に注力していくという意志と、単なる調査開発にとどまらず、お客様の課題解決につながるテクノロジーの提供に注力していくという、当社の今後の方向性に対する姿勢を表しています。
この時代、IP Geolocation技術は「位置を推定する技術」から、「誰が・どのように・どこから」アクセスしているのかを多面的に把握するIP Intelligenceへと進化を遂げました。
単に地理情報を取得するだけではなく、組織属性や通信手段、匿名性、リスク傾向などを多層的に分析できる技術へと成長しています。
当社では、法人番号・気象データ・マーケットデータなど、IPアドレスに付随する多様な属性情報を連携可能とし、データベース全体の拡張を加速。
取得可能なIP属性情報は100項目を超えるまでに増加し、より高度な判断・制御・分析に活用されるようになりました。
また、世界的にサイバーセキュリティリスクが増加する中、TorやVPNといった匿名性の高いIPアドレスを判定する「匿名ネットワーク属性」の整備を進め、アクセスのリスク可視化を実現しました。
これにより、IPアドレスの匿名性を判定する「匿名ネットワーク属性」を新たにリリースし、セキュリティ対策の現場で高い評価を受けています。
IP Geolocation技術はこの時期、マーケティングとセキュリティの両領域において、業界横断的に導入が進み、現代インターネット社会を支える不可欠な情報基盤となりました。
当社は、その根幹を担うデータベンダーとしての責任を強く認識し、技術と品質の両面において、常に最高水準を目指し続けています。
2020年代
5Gとクラウド時代の
IP Geolocation技術

2020年代に入ると、5Gの本格展開とクラウドネイティブ技術の浸透により、インターネットの利用形態はさらに多様化しました。
リモートワークやオンライン教育、動画ストリーミングの拡大により、IPアドレスを介した通信の役割もより重要性を増しています。
こうした環境下で、IP Geolocation技術はセキュリティ・DX・マーケティングといったあらゆる分野の基盤として再評価されつつあります。
通信技術の変遷
- 2020年:5G商用サービスが国内キャリアでスタート。通信の超高速・低遅延が現実のものに。
- 自宅やオフィス以外でも高速通信が可能となり、IoTデバイスの普及が加速。
- Wi-Fi 6の導入が進み、家庭内ネットワークの高速化と多端末同時接続への対応が強化。
- ローカル5GやプライベートLTEなど、企業・自治体独自の通信インフラ整備が進む。
IPアドレス環境の変化
- モバイル通信の主流がIPv6に移行。Android・iOSともにIPv6対応アプリが標準化。
- CGN(キャリアグレードNAT)の利用増加により、IPv4アドレスベースの精度把握が困難なケースが拡大。
- IPv6の国内普及率が50%を超える(2024年時点、Google IPv6統計より)。
- 一方で、クラウドやVPN経由のトラフィックが増え、IPアドレス単体での正確な判定が難化するケースも。
IP Geolocation技術の軌跡

2020年代に入り、インターネット上のデータ流通量は飛躍的に増加しました。
これに対応すべく、当社は膨大なデータをリアルタイムかつ精緻に分析できるビッグデータ分析基盤を構築し、IP Geolocation技術のさらなる高度化を進めています。
各種データソースから収集される、都市・回線・組織・匿名性といった異なる粒度の情報を多角的に突き合わせることで、IPアドレスに対して正確な属性情報を付与する仕組みを整備しました。
特に、IPv4とIPv6のデュアルスタック環境下でも安定した属性判定を可能とし、従来は特定が難しかったIPv6アドレスにも確実にリーチしています。
また、AI技術を積極的に取り入れ、過去のパターンから人間では気づきにくい傾向を抽出することで、位置情報の精度を一段と引き上げました。
これにより、従来のルールベースでは困難だった複雑なネットワーク構造においても、的確な分類と判定が可能になっています。
当社は、通信技術やネットワークの構造がいかに進化しようとも、それに適応した情報精度を保ち続けることを使命としています。
当社のIPデータベースは、インターネット上で行われるあらゆる通信を対象に、網羅的、かつ、信頼性のある情報を提供しています。
この圧倒的な網羅性こそが、IP Geolocation技術の真価であり、Geolocation Technologyの揺るぎない強みです。
今後も当社は、変化する時代の先を読み、社会に不可欠な情報基盤を提供し続けてまいります。
これからのGeolocation Technology

創立から25年、Geolocation TechnologyはIPアドレスから位置や属性を把握する技術を磨き続け、社会に役立つ情報基盤として進化させてきました。
IPv6や5Gの普及、クラウドやAIの進展により、インターネット環境はより複雑になっていますが、私たちはどんな時代の変化にも対応し、正確で実用性のあるIPデータを提供し続けています。
IP Geolocationの活用は、セキュリティ・マーケティング・アクセス制御など多岐にわたり、その信頼性と網羅性は今や不可欠な要素となりました。
私たちは今後も、ユーザーの匿名性やプライバシー保護を重視しながら、正確なデータ提供を通じて、より便利で安全なインターネットの実現に貢献してまいります。